トップページに戻る |
自然保護論(平成22年度秋学期)
〜生物多様性の保全を考える〜 |
授業の目的
自然はこれまでの人間の活動によって農地や都市などのために開発され、世界的に自然は減少傾向にあります。しかし、自然は、水源の保全や洪水の防止など地域の人々の生活にとって重要であるだけでなく、野生生物の保全、さらには地球温暖化の原因とされている二酸化炭素などの吸収源としても人類の生存に不可欠な役割を担っています。本講義では、自然の保護のための日本の政策や企業の取組などの現状と課題、世界的な自然保護の取組などについて講義し、自然保護の在り方を考えます。
授業の概要
本授業では、自然保護を生物多様性の保全(地球上に様々な種類の生物が生きており、生態系の多様性、種の多様性、遺伝子の多様性を含めてその保全を考えること)の視点から捉えます。最初に、生物多様性が人間にもたらしている様々な恩恵や、その世界の現状を説明します。その後、日本の森林、湿地などの自然生態系や野生動植物の保護の現状と課題を見ます。次に、企業活動が生物多様性へどのような影響を与えているかを概観し、これを基に、企業の生物多様性に対する責任とはなにか、企業の取組みをどのように評価したらよいかについて考えます。また、企業とNGOとの協働の可能性について検討します。最後に、人間活動が生物多様性へ与える影響を軽減していくための政府の役割は何か、今後の政策はどうあるべきかについて考えます。
授業スケジュール
1回 イントロダクション
2回 生物多様性とは何か
3回 国際社会の取組(生物多様性条約などの概要)
4回 日本の現状(1)森林の保護(白神山地のブナの原生林などの保護)
5回 日本の現状(2)湿地の保護(諫早湾などの干潟干拓事業の問題など)
6回 日本の現状(3)自然景観の保護(国立公園制度など)
7回 日本の現状(4)野生動植物の保護(コウノトリなどの絶滅危惧種の保護)
8回 企業の取組の現状(企業が自主的に取り組んでいる現状を学び、その課題を検討する)
9回 企業の責任(企業の生物多様性に対する責任について考える)
10回 企業の取組の評価(市民の視点から企業の取組みをどのように評価したらよいのか)
11回 企業とNGOの協働(企業とNGOが協働する可能性について考える)
12回 環境影響評価(開発が環境へ与える影響を事前に評価し、それを軽減するための市民参加のプロセスを学ぶ)
13回 ノーネットロス政策(開発が生物多様性へ与える影響を実質的にゼロとすることができるのか)
14回 生物多様性保全政策(日本の政策課題とその解決方法について考える)
15回 まとめ
授業の運営方法
基本的にはテキストに従って講義形式で行います。中間段階で1回レポート提出を求めます。外部講師による講義を1回程度予定しています。
評価方法
出席(25%)、中間レポート(25%)、期末試験(50%)にて評価します。
テキスト
生物多様性とCSR−企業・市民・政府の協働を考える/宮崎正浩・籾井まり/信山社/2010年4月(予定)
参考文献
自然保護法講義第2版/畠山武道/北海道大学図書刊行会/2004年/2940円(税込)
生態学からみた野生生物の保護と法律/日本自然保護協会編/講談社サイエンティフィック/2003年/3990円(税込)
|
トップページに戻る
|
|
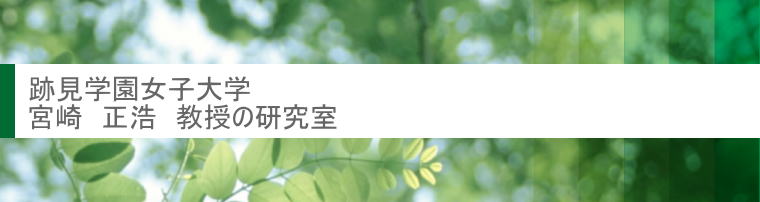
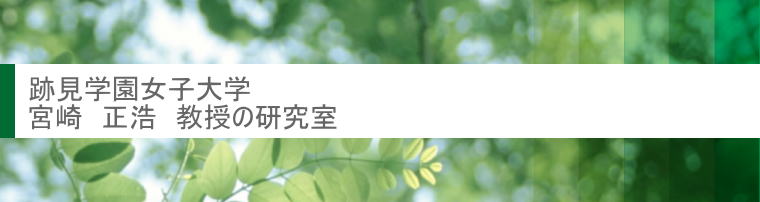
![]()